根源へ
「根源へPartⅡ-1」展開催のお知らせと出品者紹介[3] - sasayama URL
2018/09/18 (Tue) 17:41:02
 陶芸家 花塚愛は大学を卒業したのが他の二人よりは10年ほど早く、作品発表の場数も相応の回数を踏んでいます。
陶芸家 花塚愛は大学を卒業したのが他の二人よりは10年ほど早く、作品発表の場数も相応の回数を踏んでいます。
私が彼女と出会うのは1年半ほど前で、それまで彼女の活動をまったく知らずにいました。
先日、アトリエを訪ねて、大学在学中からこれまでの作歴を画像で拝見したのですが、1点1点よく作り込んでいるし、
試行錯誤もいろいろと重ねてきていることがよくわかりました。
作品1点1点の密度がかなり高いので、大変なエネルギーだと思われますが、
本人は「ふつうにやってます」という感じで、いたって淡々としています。
しかし考えてみればそれも当然のことであるのかもしれません。
というのは、生命の泉は「汲めば汲むほどますます豊かに湧き出してくる」ことを本質とするからです。
ネタが切れるだのアイデアが枯渇するだのといったことは、もともとその程度の才能であり、生命力でしかなく、
一生懸命に生きることをサボってきたことを表明しているにすぎません。
そういう花塚のステートメントにも、次のような記述が見られます。
「草花も動物もみんなこの土の上にふつうにしているということが、私には大事なことでした。時間は円を描きながら、全体がゆっくりと流れてゆくのを見つめて、毎日をふつうに生きてふつうにつくりたいと思います。」
ここには、一見だれでもが書けそうな、ふつうのことが書かれています。
でも一箇所、「時間は円を描きながら、全体がゆっくりと流れてゆく」というフレーズがちょっと気になります。
こういう言葉は、意外と“ふつう”の人からは出てこないかもしれません。
「時間は円を描く」という感覚は、観念としては理解できても、
それを自分自身の生命感のイメージとして実感している人は少ないように思います。
花塚のような若い人は特にそうでしょう。
今回の展覧会への出品作は、画像作品のように、大枠として左右シンメトリーな瓶のような形のものが出品されるとのことです。
このような円形で左右対称を基調とする作品は、昨年私と花塚が出会うきっかけとなった、
神奈川県美術展工芸部での大賞受賞作品あたりから作られ始めたようです。
それまでの作調は非シンメトリックで彫刻的であったのですが、
いわゆる器型の、自己完結するような形のものが作られ始めたわけです(そこに装飾が饒舌にほどこされていく)。
花塚の場合、この形は「時間は円を描く」という実感から出てきているように思えます。
そして彼女の中で一つの確信的認識にまで高まってきているのではないでしょうか?
そういうメッセージを強烈に打ち出そうとしている作品のように私には感じられます。
画像は、花塚 愛作「木と陽」(「根源へ展」出品予定)
「根源へ展」PartⅡ-1
会期:9月24日(月)~29日(土)
会場:ギャルリ・プス(東京都・中央区-14)5-14-16 銀座アビタシオン201)
出品者:花塚 愛(陶芸)・安田萌音(平面)・吉田麻未(ミクスト・メディア)
ギャラリー・トーク:9月27日4:00p.m.~ 会場にて
「根源へPartⅡ-1」展開催のお知らせと出品者紹介[2] - sasayama URL
2018/09/07 (Fri) 17:57:22
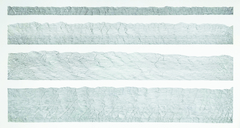 吉田麻未はステートメントに
吉田麻未はステートメントに
「視覚的に「魅力的なもの」と感じる根源的なところを求めたいというのが私の現在の動機です。」
と書いています。そして、求めていくにあたって次のような仮定を設定しています。
「それらは(自然のものも人の手によるものも)必ず意図と制約とが積み重なった結果として現れた形であるから魅力的なのだと仮定しました。」
ここで、「意図と制約とが積み重なった結果」という文言が注意を引きます。それゆえにこそ「魅力的」というわけです。
こういう思考法に吉田の特徴が見られると思います。
一昨年の個展のときに発表したステートメントには、こんなふうに書いていました。
「幼い頃のある日、眠りにつく少し前の静かな時間。ふと自分の手を見つめ、握ったり開いたりを繰り返しました。この手は私が動かしている。でも、一本一本の指のことを考えなくても、握ることも開くこともできている。手を見つめながら考えるほど、自分の頭の中と体が分かれていくような気持ち悪さがあり、怖くなって考えるのをやめました。」
この感覚は成人していくにつれて薄れていったとのことですが、彼女の原体験として、根っこの深いところにずうっと残ってきているんですね。
そういう、いわば本源的な違和感に向き合うということが創作の動機になっているわけです。
「私」は「私である」部分と「私でない」部分とで成り立っていると考えることができます。
「私である」部分は、何事かが自分の意思(意図)によってなされていると感じられる部分であり、
「私でない」部分は、何事かが自分の意思からは離れて(しかし確かに私の身体を媒介として)進行していることを感じる部分です。
その両者はどういう関係にあるんでしょうか?
こういう問いは、人間の歴史の中で、ある意味で古くから存在している問いであると思います。
そして問われるたびに、新しい問いとして問い直されていく問いでもあります。
いずれにしても、吉田の作品は、この問いに向き合って彼女なりの試行錯誤を重ねていく、
その行跡にほかなりません。
画像は展覧会出品作「homeostasis」紙にインクの線描
「根源へPartⅡ-1」展開催のお知らせと出品者紹介[1] - sasayama URL
2018/08/29 (Wed) 10:27:04
 ご無沙汰しました。当掲示板を再開します。
ご無沙汰しました。当掲示板を再開します。
9月24日(月)から、「根源へPartⅡ-1」展を開催します。
会期:9月24日(月)~29日(土)
会場:ギャルリ・プス(東京都・中央区-14)5-14-16 銀座アビタシオン201)
出品者:花塚 愛(陶芸)・安田萌音(平面)・吉田麻未(ミクスト・メディア)
ギャラリー・トーク:9月27日4:00p.m.~ 会場にて
リーフレットを制作して出品者の紹介と、各々のステートメントを掲載していますが、
ここではそのステートメントを手がかりとして、考察を展開していくことにします。
今回は、安田萌音を取り上げます。
彼は多摩美術大学で日本画を専攻し、昨年大学院を修了しています。
在学中から東京都心のギャラリーで個展を2回ほど開催しています。
日本画を描いているというよりは、日本画の枠を逸脱していこうとする傾向を示しています。
ステートメントには、「根源へ展」に向けての抱負として次のように書いています。
「自然を模倣するのではなく、絵画の中で自然を再構築することで自然美を表現することを試みる。
(中略)
私は絵画の中に大地を再構築したのだ。」
それで、ボードに目の粗い麻袋を貼って生の(絵画用に精製されていない)原土を厚く塗りたくり、その乾燥過程を通して土の表情が変化していくのをそのまま見せるような制作をしています。
そのステートメントから私は、若林奮という彫刻家が「彫刻で森を創る」というフレーズを遺していることを思い出しました。
若林は、若い頃には「彫刻で鉄を創る」という言葉も遺しています。
安田の制作は、先例として、近いところでは洋画家の宮崎進の作品があるし、私が若かった頃の1960年代~80年代においてはたまさかに見られる画風のものです。
その経験を経ている者の目からすれば、特に新しさを感じさせるものではないですが、
「絵画の中に大地を再構築する」というコンセプトにおいて、その志向するところの目新しさが感じられます。
それは一つの物質的(自然)世界を創ろうとする志向であって、「絵画の中に自然を写し取る」あるいは「自然を表現する」ということとは異なっています。
ただそのような志向が、これからの絵画にとってどういう意味を見出していくことになるのかについては、
これからの長い探求の年月が待っているように思われます。
そのことに地道に付き合っていく、というか、そのプロセスを見守っていくということ自体もそれなりに興味の持てるところです。
今日の平面表現の問題設定は、「平面で何ができるか」というよりも、「平面(2次元空間)をどう作るか」というところにあるのではないかという気がしています。
「鉄で彫刻を作る」のではなくて、「彫刻で鉄を作る」という発想ですね。
物質としての平面(2次元空間)です。
これをどう創っていくかというところに、現代絵画の問題を設定することができるでしょう。
安田の制作もこのことにどう繋がっていけるかというところに、これからの展開の楽しみがあるように感じられます。
画像は、安田萌音出品作「行為の記録ー唸りー」
第3回「根源へ」展出品者の解説(6)黒沼大泰② - sasayama URL
2018/04/21 (Sat) 22:09:11

黒沼君のやろうとしてることは、一見伝統回帰的で紋切り型のように見えるかもしれないけれども、
実はそうではなくて、図像の作り方などはコンピュータのシステムを活用して、
見え方としてはやはりどこか「見たことがない」と感じさせるところがあります。
言い換えれば、コンピュータの機能を使わなければできない図像を作っているわけです。
彼の場合、コンピュータの導入は決して作業の効率化のためではなく、
図像の創作の本質的な部分にかかわっています。
しかし他方で、金箔をピカピカに磨いていくために、メノウ棒という道具を使って手作業を積み重ねていく、ということもやっている。
コンピュータによる加工と手作業、伝統的な素材・技法と現代の素材・技法とのミックス、といったことに黒沼君は十分に自覚的なのです。
そしてそこに彼の絵画創作の新しさを認めることができます。
一見伝統回帰的で紋切り型のように見えながら、そのような見かけを通して実は日本の新しい絵画を作っていこうとしているのだと、私は見ています。
画像は、多摩美術大学内で開催された卒業制作展のときの作品展示の様子を写したもの。
第3回「根源へ」展出品者の解説(5)黒沼大泰① - sasayama URL
2018/04/12 (Thu) 17:53:14
 今回の「根源へ展」の出品者のことは昨年の秋に一度紹介してますが、
今回の「根源へ展」の出品者のことは昨年の秋に一度紹介してますが、
黒沼君については、「花鳥風月という伝統的な美術表現が現代の日本人の美的感性のリアリティを形成している」として、そのリアリティに立ち向かっていく道筋にも現代美術のひとつの方向があり得るといった意味のことを書きました。
具体的には、「光琳から始めるべき」ということで、当時彼は4年生で卒業制作にとりかか
っていました。
梅の木をモチーフに画面全面に金箔を貼り、図像の部分はアクリル絵の具で描くという方法で、縦横120cm弱の大作です。
一見伝統的な花鳥画のように見えるのですが、アクリル絵の具で描かれた梅の木の部分と金地との対比で空間の奥行き感や木の存在感をアピールしていたり、
絵を作っていく過程でコンピュータを活用しつつ、他方で伝統的な技法を手作業で積み重ねていくなど、さまざまな工夫が見られます。
それが何か今までにないビジョンを創り出しているように感じられます。
ただヴィジョンが新鮮というだけでなく、「絵画の在り方」ということについても一石を投じています。
というのは、金箔の光を反射する性質をポジティブに捉えて、作品の要素として内在化していると思われることがあるのです。
たとえば、スポットライトを当てると、作品の中に反射光の輪のようなものができますが、
彼の作品の場合、それがもうひとつ別な絵画作品のように見られるのです。
また、斜めの角度から見ると、梅の木の図像が画面全体が光り輝く中に、まったく違ったイメージで見えてきたりします。
まさに作品が置かれている周囲の環境を、光を媒体として取り込むことによって、
さまざまに変幻していくわけです。
絵画を単に均質な光の中で固定的に見るのではなしに、環境とともに在るものとしてみていく、
そこから「生活に結びついた絵画」のひとつの可能性が提示されているように思われるのです。
掲載画像は黒沼君の卒業制作作品で、スポットライトの反射光がなにやら意味深な雰囲気を醸し出している例。
「根源へ展」の開催は
4月23日(月)ー28日(土)
ギャルリ・プス 中央区銀座5-14-16 銀座アビタシオン201
最終日午後3時よりトークセッションあります。
第3回「根源へ」展出品者の解説(4)仲田有希② - sasayama URL
2018/04/06 (Fri) 17:50:57
 掲載画像の作品「庭へ」は油彩画で、一見したところでは特に変わったところのない普通の絵のように見えます。
掲載画像の作品「庭へ」は油彩画で、一見したところでは特に変わったところのない普通の絵のように見えます。
少し分析を試みると、まず第一に、実写した絵ではなく、描かれているシーンは想像上のものであると見なすのが自然でしょう。
窓が描かれていて、手前が室内と想定されます。そして何本かの百合の花が窓から侵入してくるような光景として描かれています。
実写の絵ではないので写実画とは言いがたく、空想上の、あるいは装飾的な効果が意図された絵と見なせるでしょう。
おそらくこの絵は、アタッシュケースの内部に描かれることを想定して描かれたのではないかと、想像することが可能です。
そういうことを意図して描かれた、装飾的な絵と見ることが可能です。
前回書いたように、作者仲田さんは、絵を四角い額縁の中に収めて見るものとして考えていません。
とりあえずはアタッシュケースの内部を装飾する絵として、あるいは、アタッシュケースによって持ち運びされる絵として構想していると思われます。
絵それ自体の中にも、いわば限定された縁とか枠とかの境界を逸脱して、内と外(室内と庭)を自由に行き交うような、運動の在りようが空想されているように受け取れるのですね。
境界を曖昧化する、あるいは境界を消去する、そのような行為や意図において絵作り(表現)を成り立たせようとする、
そういうたくらみが仲田さんの創作のテーマとして考えられそうです。
境界の曖昧化というテーマは、まさに日本文化の伝統に深いルーツが認められます。
最近私が得た知識ですが、古代の平城京には城壁が作られなかったということですが、
城壁のない古代・中世都市というのは、世界の歴史においても、他に例を見ないとのことです。
日本の文化的風土において、境界の曖昧さということは、すでに古代の時代から実現されていたのですね。
掲載画像は、仲田有希作「庭へ」油彩画
第3回「根源へ」展出品者の解説(3)仲田有希① - sasayama URL
2018/03/30 (Fri) 16:06:29
 仲田有希さん(油画専攻4年)は、『現代工芸論』の中で特に造形論で論じられる「物質の限界を超えていかなければ先に進めない」という命題に関心を抱いたようです。
仲田有希さん(油画専攻4年)は、『現代工芸論』の中で特に造形論で論じられる「物質の限界を超えていかなければ先に進めない」という命題に関心を抱いたようです。
過去2回の「根源へ展」でも毎回この命題に関心を向けた学生がいましたが、
そのアプローチはそれぞれまったく異なっています。
ある意味、抽象的なテーマなので、解釈も多様にありうるのですね。
仲田さんは、物質と意識(精神)が交感するような事態としてイメージしたようです。
講義のレポートではこんなふうに書いていました。
「物質と人が交差するとき、「“何か今明らかに違うものになった”と感じられることがある。絵を描いている時にも、立体物を作っている時にも、それは自らの手中でコントロールしているのではなく、別の次元で物質が作用していることがある。濡れた絵の具が乾く時なのか? つなぎ合わさった木と木がなじんだと感じる時か? それらは私が作品を作るときの目に見えづらく、言葉にしがたい神秘だと思っていた。」
リーフレットに掲載している作品写真は、壁面を利用したインスタレーション風の作品です。
床の上には、仲田さんが自分で作ったアタッシュケースが置かれています。
その中には絵が描かれているのですが、アタッシュケースの制作の意味を以下のように書いてます。
「アタッシュケースの持ち手を握ることで、絵画と手を取り合うといった意味を含ませた」
アタッシュケースの持ち手を握るということは、アタッシュケースを持ち運ぶということです。それは「絵を持ち運ぶ」ということでもあります。
“絵画”を四角い額縁の中に収めて鑑賞するものとして固定的に捉えずに、
持ち運べるもの、としても考えてみる。
ここに“物質の限界を超える”という命題とのかかわりが読み取れます。
もっとも、アタッシュケースの中に描かれた絵、ということでは、
モノを装飾するはたらきのあるものとして絵画を見ているに過ぎないのでは、と思われるかもしれませんが、
そうだとすれば単なる装飾画あるいはイラスト絵画ということになるのですが、
仲田さんが考えていることはそうではなくて、
人の生活一般とか、行動とか、そういった意識の運動の中に差し挟まれていく絵画、といったようなニュアンスで考えているように思われます。
ちょっと微妙ですが、それがどういう意味合いを持ってくるのか、
次回、さらに考えていくことにししましょう。
画像は壁面を使ったインスタレーション「自由と束縛」
第3回「根源へ」展出品者の解説(2)寺松尚美② - sasayama URL
2018/03/22 (Thu) 17:55:19
 出品者の作品資料としてこれまでに制作してきたものの画像データとコメントを、
出品者の作品資料としてこれまでに制作してきたものの画像データとコメントを、
各出品者から提供してもらったのですが、その際、寺松さんが送ってきた画像には、
それぞれに短いメッセージが添えられていました。
それをここで紹介しておきます。
「咲き続く」(前回画像を掲載した作品)には、
「私たちは変化していくが、存在していた一瞬一瞬は記憶の中で生き続ける。
花のように咲くその記憶をいつまでも忘れないことで、私たちは安心してその手を握ることができる。」
「柱になる」(今回掲載の作品)には、
「私たちには木の幹のような変わらない部分がある。
人は常に変わっていくが、その部分を忘れないようにしたい。私たちは安心してその手を握ることができる。」
これをどう読むかということですが‥‥、
寺松さんの創作がこれからもずうっと続いていくとしたら、
何十年も先になってこのメッセージを読み返したときに、
ここに寺松さんの創作の軌跡を貫いてきた根本的なテーマが、
凝縮して表現されている、というふうに読めることでしょう。
そういう観点から、このメッセージに込められている寺松さんの根本テーマはなんだろうかと憶測してみるのも、興味深いものがあります。
六十数年を生きてきた私が思うに、若いときの記憶を維持していくことは、
それがよほど強い印象で残っていない限りは、はなはだ困難なことです。
人には「木の幹のような変わらない部分がある」ことは確かですが、
「変わらない部分」の認識の仕方、あるいはその意味付けはやはり変わっていくのが一般的です。
その場合に「変わらない部分」と思っていたものは、どうなっていくのか?
「変わらない部分を忘れないようにしていく」こと、「記憶をいつまでも忘れないでいること」とは、そのような意味でとても困難なことなのです。
しかしその困難さに立ち向かって、いわば“忘却”いう事態と戦っていくことが、
まさにアートと呼ばれるものの営みにほかなりません。
忘れさえしなければいい、というものでもありません。
そこに新しい意味を見出しながら記憶を更新していくという形もありえます。
そうして「安心して手を握る」世界が実現できたら、
それはとても素晴らしいことであると思います。
画像は寺松尚美作「柱になる」
展覧会の詳細は上記「URL」(タイトル欄の中)からアクセスできます。
第3回「根源へ」展出品者の解説(1)寺松尚美① - sasayama URL
2018/03/16 (Fri) 16:32:03

これから来月の「根源へ展」の開催間近あたりまで、出品者の作品やコメントをめぐって、
思うところを書いていくことにします。
トップバッターは寺松尚美さん(工芸学科ガラス専攻4年)です。彼女が「現代工芸論」から得たことは――、
工芸の全体は「民衆の生活に即した用の美を目指すもの、国家的事業あるいは権力者のステータスシンボルとして美の究極を追求していくもの、個人による創作、の3つの分野に分けられる」として、そのことを踏まえた上で、「自分が作ろうとしているのは何なのか」を問いかけるものでした。
現代工芸の分野では、工芸と美術はどう区別されるのか、ということがよく話題になります。
たいていは、「使えるものを作るのが工芸」、「使えないもの(用途のない純粋に美的なもの)を表現するのが美術」というふうに区別されるのですが、
現代工芸の分野では「使えないもの」も“オブジェ”と称して創作する一方で、オブジェか器的なものかどちらかに創るものを限定すべきではないか、という考えも頑なにあるようです。
私はこのような二者択一的な限定を強いるのは、今日の工芸的創作においてはほとんど無意味であると考えています。
オブジェには鑑賞物という用途がありますし(現代工芸で使用される“オブジェ”と、現代美術の“オブジェ”とは意味内容が異なっています)、
器の形には用途を超えた美しさを有することは、改まって言うまでもありません。
そもそも古典の時代から「工芸品」とみなされてきているものが工業製品と違っているところは、
それがなにがしか特殊な状況下で作られてきている点にあって、
民芸派の人々が“雑器”と呼ぶものも、彼らの審美眼によって選別されてきたという特殊事情を担っています。
個人による制作ということも、ひとつの“特殊的状況”なのでありますから、器のものを作るにしろ、オブジェ的なものを作るにしろ、“個人”という創作主体の特殊性を踏まえた上での制作であればなんでもいいんじゃないですか、というのが私の見解です。
寺松さんはその考え方を取得して、自分の進むべき方向を探り出していこうとしているのだと思います。
画像は寺松尚美作のガラス作品「咲き続く」
展覧会の詳細は上記「URL」よりアクセスできます。